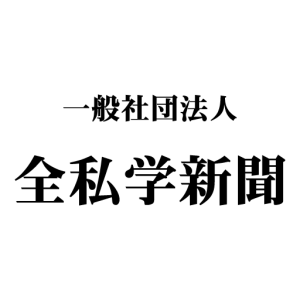第131回中教審教育課程部会を開催
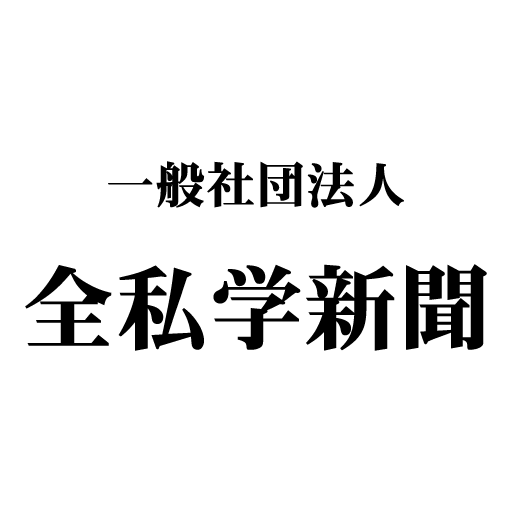
部活動の地域移行に伴う学習指導要領解説見直し等説明
文科省の中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会(部会長=奈須正裕・上智大学教授)は、10月25日、第131回部会を同省でオンラインも併用して開催した。
同省総合教育政策局学力調査室から全国学力・学習状況調査(学調)の現況の説明があり、令和6年度の学調結果の分析の一例が報告された。
社会経済的背景(SES)や主体的・対話的で深い学びと正答率の関係を分析したところ、主体的・対話的で深い学びに取り組んだ児童生徒は、SESが低い状況でも各教科の正答率が高い傾向があると分かった。また義務教育段階では理科の学力に男女差は見られないが、理科への興味・関心は男子の方が女子より高く、理系人材の育成の政策企画・立案に生かすべきと指摘している。
エビデンスに基づく学習指導のために、学調のデータを児童生徒一人一人に還元していく取り組みが進められており、国は平均正答率だけでは把握できない、学校や学級全体の課題の傾向などを見つけ出せる「学校/学級別解答状況整理表」を全学校に標準提供し、学校のDX環境や教師の分析経験に左右されず、児童生徒のつまずきや学級指導課題を把握できるよう支援している。また、学調の集計結果データを大学や公的機関などに一定期間貸与し、教育施策の改善・充実を促進させることも行っていること、今後、学調はCBT、IRT(項目反応理論)の導入が計画されていて、解答データをビッグデータとして蓄積できること、多様な方法・環境での出題・解答や、多くの問題を使用し、幅広い領域・内容での調査が可能、調査日の複数設定も可能などの多くのメリットがあることが説明された。令和9年度には全ての教科でCBT化を予定している、という。
こうした同省の説明に委員から、「全国学調と地方で独自の学調などとトータルで分析できると実態が把握でき、地域ビジョンが見えてくる」など、CBT・IRT化に期待する意見が出された。
次に部活動の地域移行に伴う学習指導要領解説の見直しについて同省から説明があった。
令和5年度から地域スポーツクラブへの地域移行に向けた実証事業が行われている。実証事業の1年目が終了し、更に円滑に実施が進むよう学習指導要領解説の見直しが予定されており、学校と地域クラブとの連携に関する記載を新設し、自主・自発的な参加であること、誰でも参加でき、複数の活動など幅広い経験ができる配慮などが加えられる予定。
この報告に対して委員からは「少子化により学校内で成立しない部活動が出てきている。教師の負担軽減を図りながら、部活の体験格差が出ないようにしたい」「スポーツ競技団体の意向が強いと、民間移行により試合に出られないケースがある。この内容をスポーツ競技団体がどう受け止めるか考えてほしい」などの意見が出された。
同省の有識者検討会で論議された今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方の論点整理の報告もあり、「個別最適な学びと協働的な学びとの一体的な充実」について、より分かりやすい整理が必要で、デジタル学習基盤を前提とした学びのデザインの方向性を示す、厚い教科書、入試などの影響を含めた授業づくりを考え、学校現場に過度な負担が生じない教育課程の仕組みの検討、総授業時数は現在以上に増やさないことの検討など、有識者会議での論点整理が報告された。
報告に対して委員からは、「地域格差、学校格差、不登校などの課題が深刻になっているので、全ての学校で取り組むべきこと、学校の裁量に委ねられることを分けて考えられるとよい」「デジタル学習基盤を前提としつつも、五感を使って活動する体験の機会も充実させたい」などの意見が聞かれた。
そのほかに会議では今後の幼児教育の教育課程、指導、評価等の在り方に関する有識者検討会での最終報告についての説明もあった。